ブログ
Blog
大学受験では予習と復習どちらが大事?合格への効率的な勉強戦略

大学受験に向けて勉強を進めている高校生にとって、「予習と復習どちらを優先すべきか」は切実なテーマです。高校受験と違い、大学受験は範囲が膨大で、学校の授業進度だけに頼っていると間に合わないのが現実です。ここでは、大学受験における予習と復習の重要性や学年ごとのバランス、効果的な勉強法について詳しく解説していきます。
1. 大学受験の特徴と勉強の課題

高校受験との大きな違いは、大学受験の範囲が圧倒的に広いことです。特に数学・英語・理科・社会などは深い理解と演習が求められ、定期テスト対策に留まる勉強では対応できません。
また、入試本番で問われるのは「知っているかどうか」ではなく「使えるかどうか」です。したがって、ただ授業を聞いて復習するだけでは足りず、自分で予習して学習を前倒しし、早めに過去問演習に入る必要があるのです。
2. 予習が大学受験で重要な理由
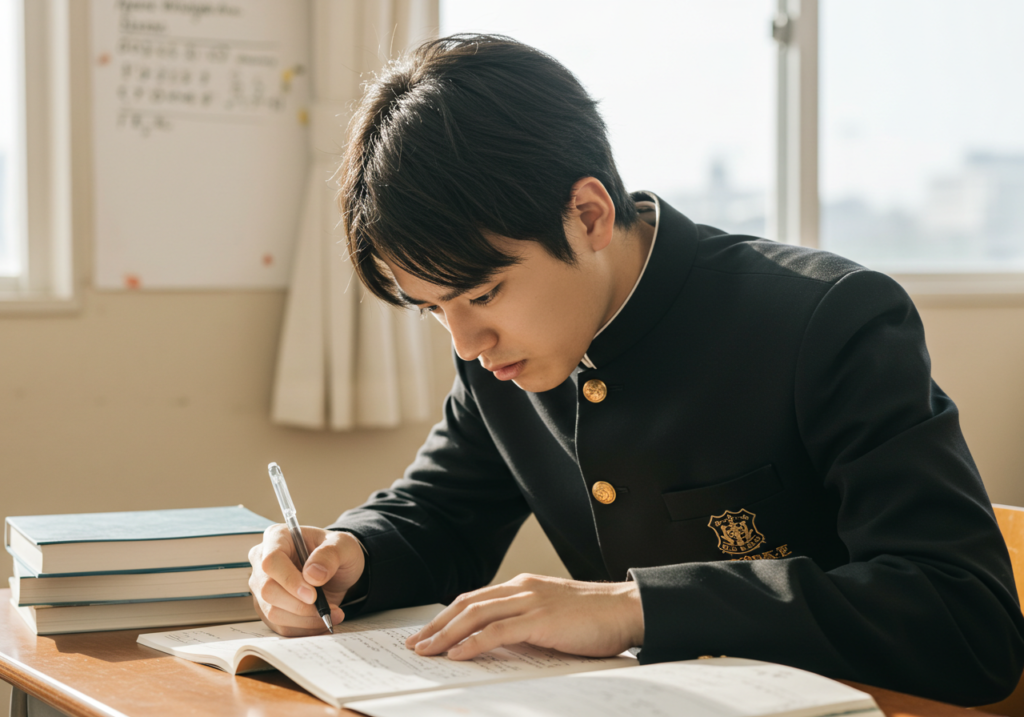
- 範囲を早く終わらせられる:高3の夏までに主要科目の学習範囲を一通り終えておかないと、秋以降に過去問対策ができません。
- 2周目・3周目に入れる:受験本番で得点力をつけるには繰り返しが不可欠。予習によって早めに1周目を終わらせることが重要。
- 応用問題に対応できる:大学入試は思考力を問う問題も多いため、予習で基礎を前倒しし、演習に十分な時間を確保する必要があります。
つまり大学受験では、「予習は合格戦略のスタートライン」といえるのです。
3. 復習の役割も欠かせない
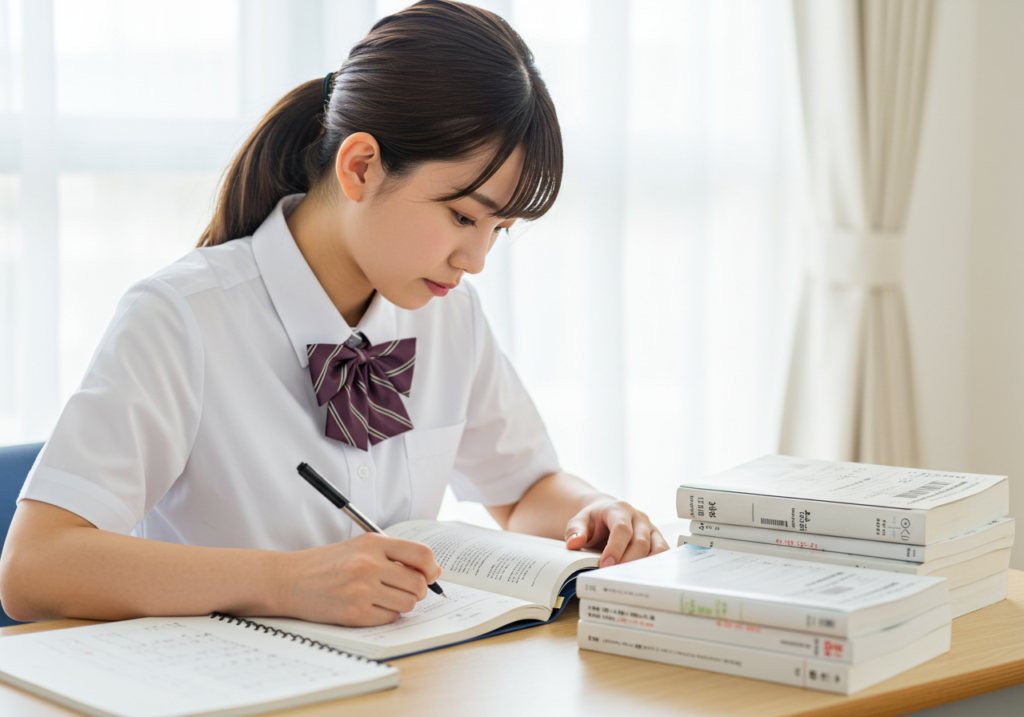
もちろん、予習ばかりに偏るのは危険です。予習で学んだ内容を定着させるのは復習の役割です。
- 理解の確認:自分で問題を解き直すことで、本当に理解できているかどうかを確かめられます。
- 記憶の定着:英単語・古文単語・化学の用語などは繰り返しの復習がなければ忘れてしまいます。
- 弱点の発見:復習を通じて「わかったつもり」で放置していた部分が明確になります。
予習で範囲を広げ、復習で力を定着させる。この両輪がそろって初めて、大学受験に通用する実力がつくのです。
4. 学年ごとの予習・復習バランス

- 高1〜高2前半:復習6割、予習4割
学校の授業理解を優先しつつ、主要科目の予習で先取りを始める。 - 高2後半〜高3夏:予習6割、復習4割
主要科目の範囲を一気に終える。高3夏までに一通り学習を終えることが目標。 - 高3秋以降:復習7割、予習3割
新しい範囲を学ぶよりも、過去問演習や模試の復習を徹底し、得点力を仕上げる段階。
5. 効率的な勉強法
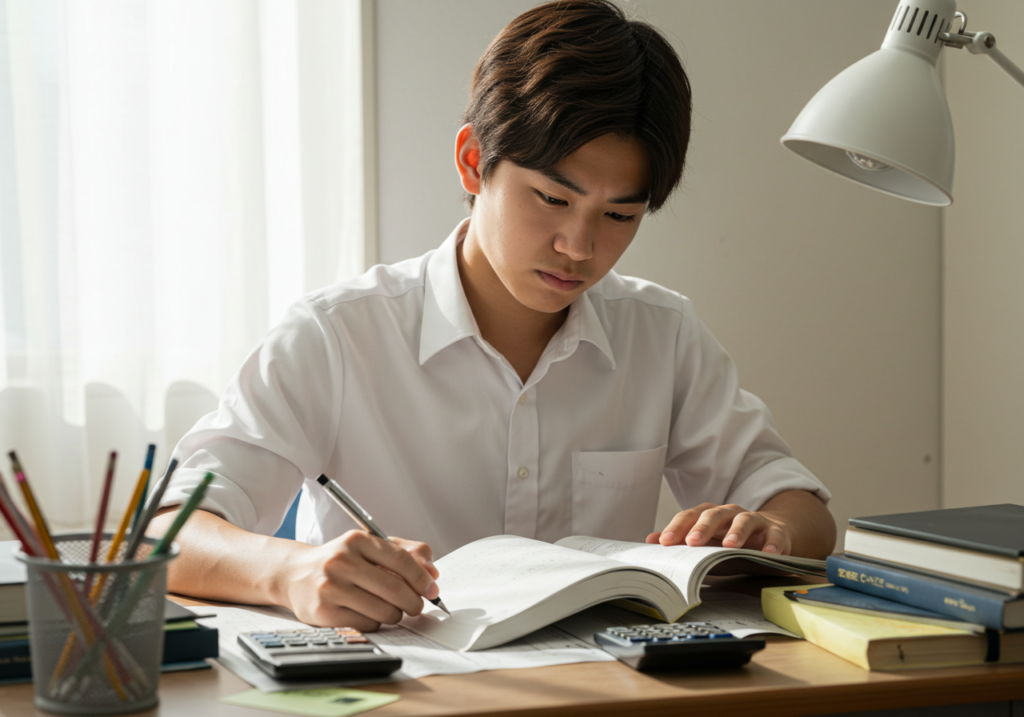
- 予習は軽く通読+例題:教科書をざっと読み、例題を一つ解く程度で十分。
- 復習は演習重視:授業内容を確認するだけでなく、自分で手を動かして解くことが不可欠。
- 逆算型計画:志望校の入試日から逆算して「高3夏までに範囲終了」「秋から過去問演習」と明確にスケジュールを立てる。
まとめ(大学受験編)

大学受験においては、予習で範囲を前倒し → 復習で定着 → 過去問演習で仕上げるという流れが王道です。
高校受験以上に範囲が広いため、特に高3夏までに主要科目の学習を終えておくことが合格の条件といえます。
復習中心の学習では間に合わず、予習だけでは定着しません。両方を戦略的に組み合わせ、効率的に進めることが大学受験合格のカギとなります。
関連記事はこちらです:
プロフィール:
和田晶平 スタディブレイン和歌山駅東口教室勉強コーチ
哲学と歴史が大好き 最近は中国古典にハマっている
スタディブレイン和歌山駅東口教室