ブログ
Blog
「やる気が出ない」は脳の仕組み?サボり癖を科学でぶっ壊す方法

◆ 勉強のやる気が出ないのは「性格」のせいじゃない
「勉強しないといけないのに、やる気が出ない…」
「今日こそやろうと思ってたのに、またスマホ触ってしまった…」
こうした悩みを「自分は意志が弱い」と責める人が多いですが、
実は**“脳の仕組み”に逆らって勉強しようとしているだけ**なのです。
やる気とは、そもそも勝手に湧いてくるものではありません。
「動いた後にやる気が出る」という逆の順番で脳は働いています。
◆ 脳科学から見る「やる気の正体」
脳の中には「側坐核(そくざかく)」という部位があります。
この部分が刺激されると、ドーパミンという“やる気ホルモン”が出て、モチベーションが高まることがわかっています。
ところが、この側坐核が動き出すには「何かしらの行動」が必要です。
つまり、
「やる気が出たから動く」ではなく、
「少し動いたからやる気が出る」
というのが、脳の本来の働きなのです。
◆ サボり癖を打破する3つの具体策
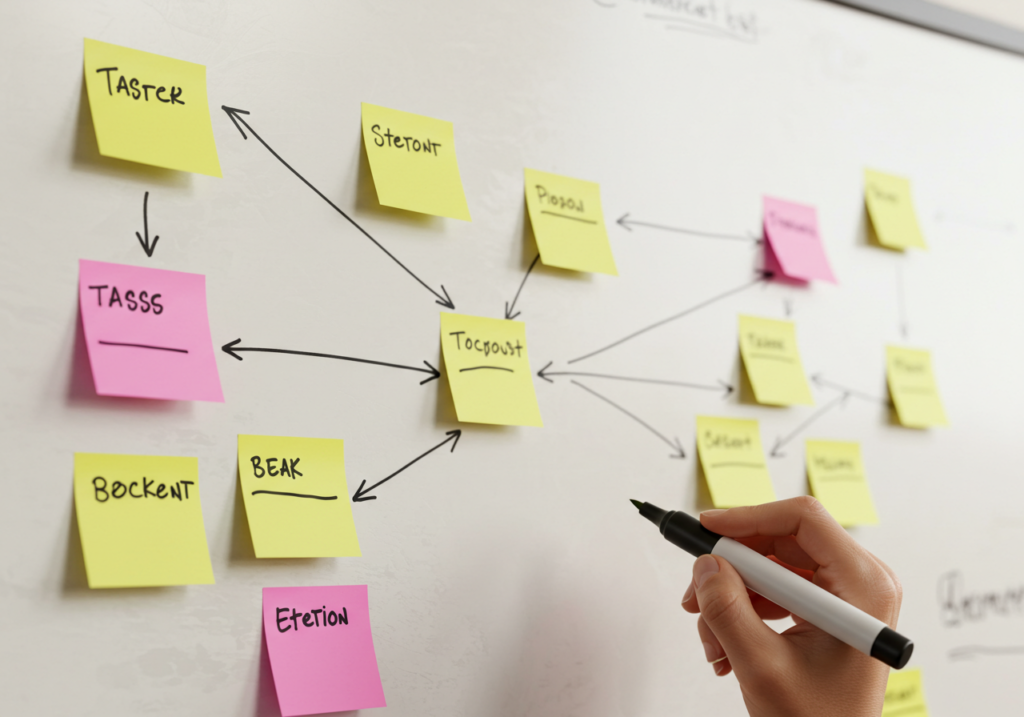
①【“始めるだけ”を目標にする】
「1時間勉強しよう」ではなく、
「とりあえず5分だけやってみる」くらいがベスト。
始めてみると、案外そのまま20分〜30分続けられることがよくあります。
これは側坐核が刺激された証拠です。
②【やることを“見える化”する】
やる気が出ない最大の原因は、「何をやればいいかよくわからない」状態。
- 今日やるページを付箋で貼る
- タスクを3つに絞って紙に書く
このように、行動を“迷わない状態”に整えることが、スタートを切るコツです。
③【報酬を先に決めておく】
脳はごほうびがあると頑張れます。
「英語を30分やったらYouTube10分」など、ルールを決めておくことで、自分の脳を上手に動かすことができます。
※ポイントは「我慢したらごほうび」ではなく「頑張ったらごほうび」とすることです。
◆ やる気の出ない自分を責めないことが一番大事

どんなに優秀な人でも、「やる気が出ない」ときは普通にあります。
一流のアスリートでさえ、「今日は練習に行きたくない」と思う日もあるのです。
でも、彼らが強いのは「動くことでエンジンがかかる」ことを知っていて、ルーティンを守っているからです。
だから、やる気が出ないときこそ、
- まずは机に向かってみる
- ノートを開くだけやってみる
- 数式を1行だけ書いてみる
こうした「小さな行動」で脳をだましてみましょう。
◆ まとめ:やる気は「行動のあと」にやってくる
- やる気が出ないのは、意志が弱いからではなく脳の性質によるものです。
- 「少し動くこと」で脳のやる気スイッチが入ります。
- 勉強のハードルを下げて、「まず5分だけやる」が最も効果的です。
- 勉強内容を見える化して、迷いをなくすことも重要です。
- 報酬を設定することで、行動とやる気の好循環が生まれます。
関連記事はこちらです:
プロフィール:
和田晶平 スタディブレイン和歌山駅東口教室勉強コーチ
哲学と歴史が大好き 最近は中国古典にハマっている
スタディブレイン和歌山駅東口教室