ブログ
Blog
「集中力ない子」なんていない!脳の仕組みを味方につけろ
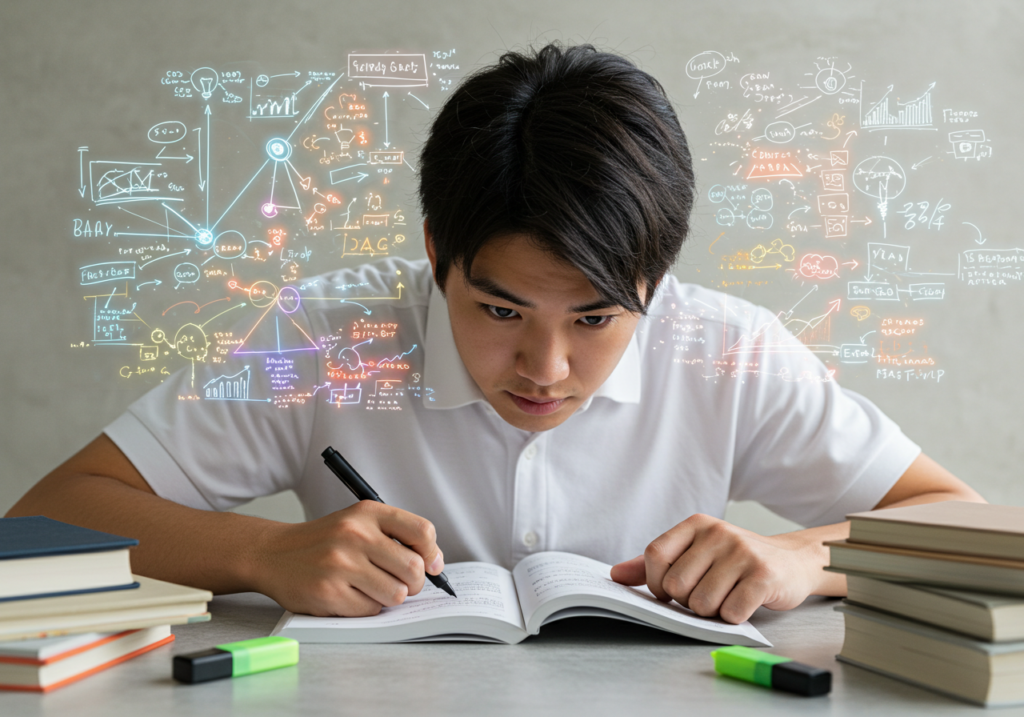
「うちの子、集中力がなくて…」
「すぐにダラダラしてしまうんです」
こんな悩みを持つ保護者の方は少なくありません。
ですが、はっきり言います。
集中力がない子なんて、いません。
ただ、“集中しやすい環境や方法”を知らないだけなのです。
今回は、脳科学や心理学の知見をもとに、誰でも集中力を引き出すための方法をご紹介します。
◆ 集中力は脳の“前頭前野”がカギ
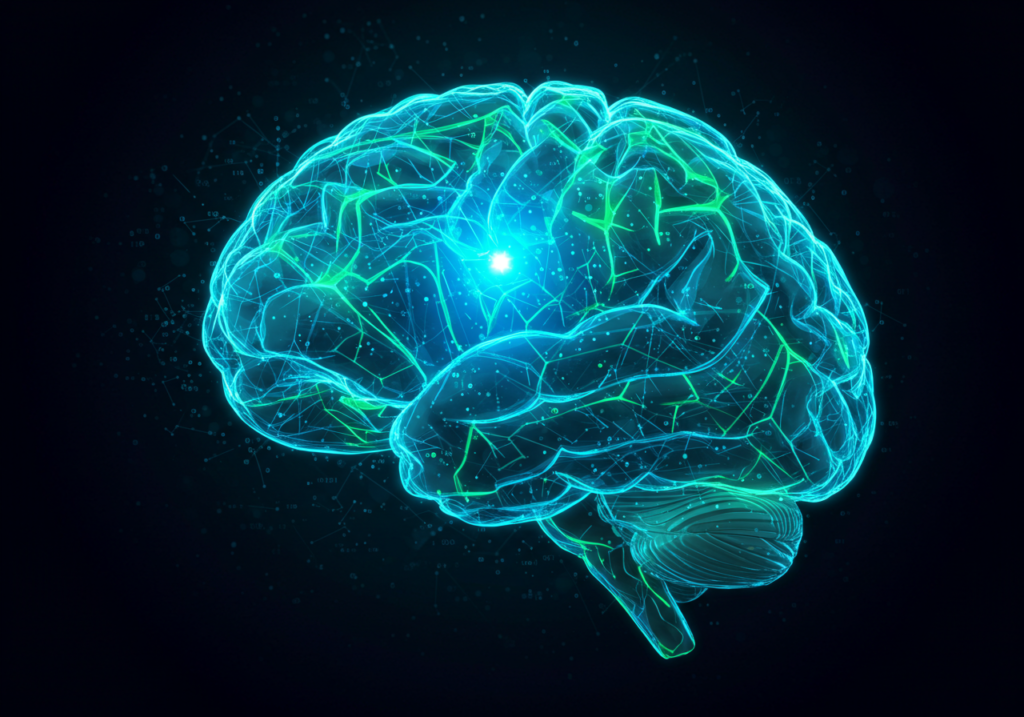
集中力は、脳の「前頭前野(ぜんとうぜんや)」という部分が大きく関わっています。
ここは思考・判断・感情のコントロールなどをつかさどる、いわば“人間らしさの中心”です。
この前頭前野は発達途中の子どもにとっては、まだ未熟。
だからこそ、集中力が長く続かないのは自然なことなのです。
◆ なぜ集中力は続かないのか?
人間の脳は、15分〜最大でも40分程度しか集中できない構造になっています。
「1時間集中しろ!」というのは、ある意味“拷問”のようなもの。
集中が切れるのは、意志が弱いからではなく、脳の疲労反応です。
ですから、集中が切れることを前提に、勉強方法や時間を設計することが大切です。
◆ 科学的に集中力を高める方法

① 時間を区切る「ポモドーロ・テクニック」
25分勉強 → 5分休憩 を1セットとして繰り返す学習法です。
この方法は、脳のリズムに合っており、短時間集中×小休憩でパフォーマンスが最大化されます。
特に中高生には「30分×4セット」などの“コマ勉強法”も効果的です。
② 軽い運動やストレッチで脳を活性化
ウォーキングやストレッチなどの軽い運動は、脳の血流を促進し、前頭前野を活性化させます。
勉強前に5分間の体操を取り入れるだけでも、集中のしやすさが大きく変わります。
③ 集中を妨げる環境を減らす
- スマホの通知音
- 雑音(特に人の声)
- 散らかった机
これらはすべて“脳の注意”を分散させます。
学習中は、機内モード・タイマーだけON・周囲は静かにがベストです。
また、ホワイトノイズや自然音(雨音・川のせせらぎなど)を活用すると、周囲の音をマスキングして集中しやすくなるという研究もあります。
④ 睡眠・食事・水分を整える
集中力はメンタルだけでなく、体調に大きく左右されます。
- 睡眠不足 → 前頭前野の機能が低下
- 空腹や脱水 → エネルギー不足で注意力ダウン
特に朝ごはんを抜いていると、午前中の集中力は著しく下がります。
**「勉強しない」ではなく「集中できない体になっている」**こともあるのです。
◆ 子どもに合った集中環境をつくるには?

集中力を育てるために大切なのは、「がんばらせること」ではありません。
以下のように、集中できる仕組みを大人が用意することが重要です。
- 時間を区切る(タイマーを活用)
- 科目や内容を細かく分けて1セットを短くする
- 休憩の使い方を工夫する(軽食・軽運動・深呼吸)
- 成功体験を積ませて「集中=気持ちいい」と覚えさせる
これらを習慣化できれば、集中力は自然と“持久力”へと成長していきます。
◆ まとめ:「集中力がない」のではなく「集中しづらいだけ」
- 集中力は脳の性質。トレーニングではなく環境設計がカギ
- 時間を短く区切ることで集中をコントロールできる
- スマホ・音・空腹など、注意を妨げる要因は意識的に排除しよう
- 集中しやすい子は“正しい習慣と工夫”を知っているだけ
「うちの子、集中力がなくて…」という悩みは、今日から解消できます。
集中できる仕組みを作ってあげることで、
誰でも「集中できる子」になれるのです。
スタディブレインでは、今回紹介したような科学的に正しい勉強法をカリキュラムに取り入れています。「集中力がない・続かない」というのは、生徒自身も保護者さんも共通して持つお悩みだと思います。
そのお悩みを解決するお手伝いを、私たちにさせてください。お問い合わせお待ちしております。
こちらもご覧ください:
プロフィール:
和田晶平 スタディブレイン和歌山駅東口教室勉強コーチ
哲学と歴史が大好き 最近は中国古典にハマっている
スタディブレイン和歌山駅東口教室