ブログ
Blog
受験生なのに自覚がない子ども…親ができる5つの意識改革法
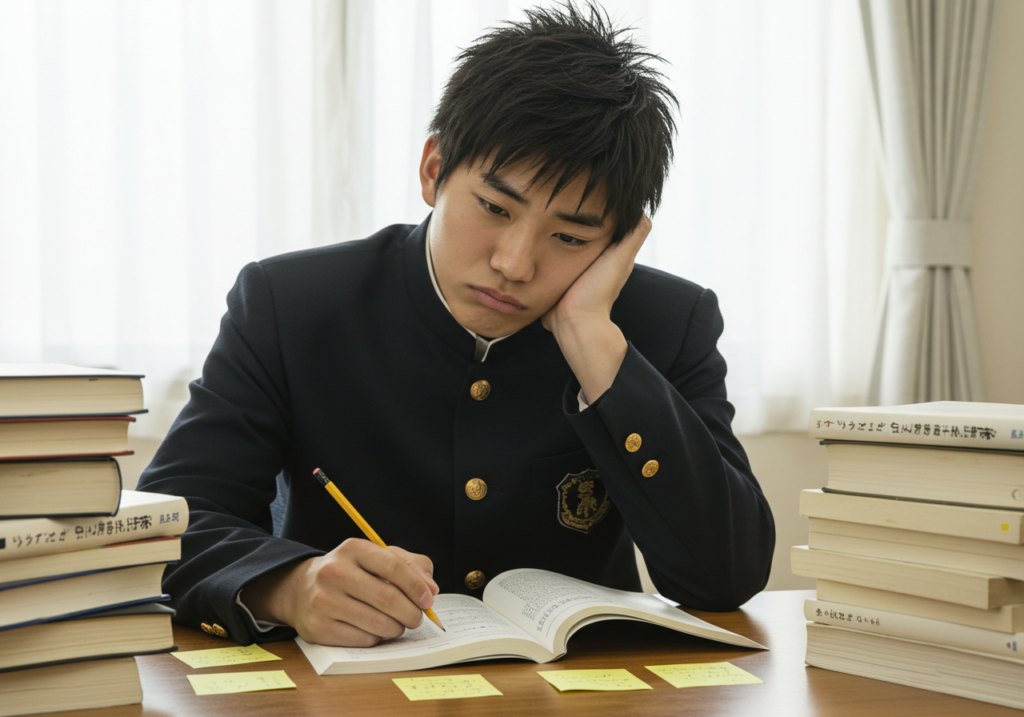
「もう受験まで半年なのに、全く焦っていない…」
「勉強よりスマホや部活ばかりで、受験生という自覚がない…」
そんな悩みを抱える保護者は少なくありません。
中学3年生や高校3年生になっても、現実味を持てず、のんびり過ごしてしまう子どもは珍しくないのです。
本記事では、なぜ受験生の自覚が芽生えないのか、その原因と心理を整理し、親ができる5つの意識改革法を具体的に解説します。
1. なぜ「受験生の自覚」が芽生えないのか?

危機感を持つ経験が少ない
これまで本気で努力しなければならない場面を経験していないと、受験も「まだ先の話」と感じやすくなります。
特に、成績が生活に直結しない中学生や高校生は、現実感が薄れがちです。
周囲の状況を比較できていない
模試や成績順位などで自分の立ち位置を知る機会が少ないと、焦りが生まれません。
また、友達も同じようにのんびりしている場合、「自分も大丈夫」と思ってしまいます。
目標が曖昧
「志望校に受かりたい」という漠然とした願望だけでは、行動につながりません。
目標が数値化されていないと、今日何をすべきかが不明確になります。
2. 親ができる5つの意識改革法
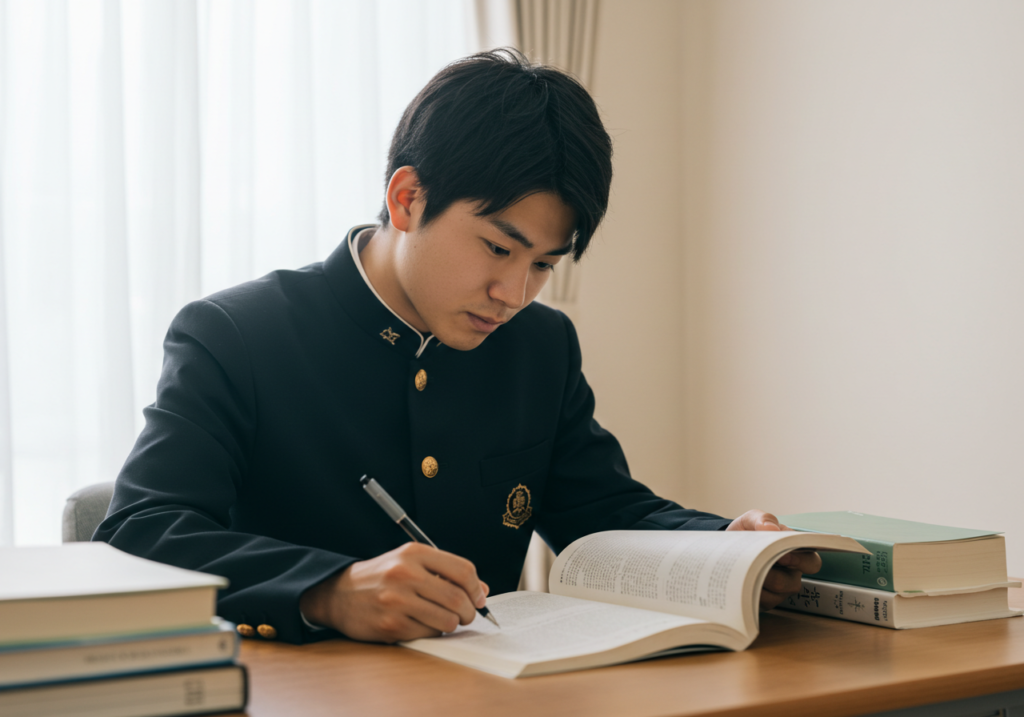
① 現状を数字で見せる
受験生の自覚を持たせる第一歩は現状把握です。
- 模試の偏差値と志望校の合格目安を比較
- 教科ごとの得意・不得意をグラフ化
- 過去問の平均点やボーダーラインを数字で提示
数字やデータを使うことで、今のままでは届かないことが“感覚”ではなく“事実”として伝わります。
② 短期目標を設定する
「本番まであと○か月」ではなく、「次の模試までに英単語100個」のような短期的・具体的な目標を設定します。
心理学でいうスモールステップ法により、達成感を積み重ねられます。
例:
- 英単語1日20個覚える
- 数学の苦手分野を1週間で3単元復習する
③ 将来像を一緒に描く
合格後の学校生活や、その先の進路を具体的にイメージさせます。
- 部活や学校行事の雰囲気
- 学びたい分野や職業とのつながり
- 友人や生活環境の変化
「合格=終わり」ではなく、「合格=新しい生活の始まり」と感じさせることで、モチベーションが上がります。
④ 第三者の刺激を利用する
親の言葉は感情的に受け止められやすく、響かないこともあります。
そこで、外部の刺激を使います。
- 先輩や塾講師の体験談
- 同じ志望校を目指す仲間との勉強会
- 学校の進路指導や面談
同年代や少し年上の人の努力や経験は、強い動機づけになります。
⑤ 成長を見える化する
- 解ける問題の数の変化
- 模試の点数や偏差値の上昇
- 学習時間の記録
「やればできる」という感覚を持たせることが、自覚を育てるカギです。
小さな進歩でも可視化してあげると、本人の中に達成感が積み重なります。
3. 親が避けたいNG対応

責めるだけの声かけ
「どうしてやらないの!」と責めると、反発心や諦めにつながります。
事実を提示し、自分で判断させる姿勢が有効です。
勉強だけを押し付ける
生活リズムの乱れは集中力や学習効率を下げます。
睡眠・食事・運動といった自己管理を整えるサポートも忘れないようにしましょう。
まとめ

受験生の自覚がない原因は、
- 現実感の欠如
- 比較対象の不足
- 目標の不明確さ
にあります。
親ができるのは、
- 現状を数字で見せる
- 短期目標を設定する
- 将来像を描かせる
- 第三者の刺激を利用する
- 成長を見える化する
の5つの意識改革法です。
受験は、本人が本気になった瞬間から大きく変わります。
そのスイッチを押すのは、日々そばで見守る保護者の関わり方です。
今日からできる小さな一歩を、一緒に始めてみましょう。
関連記事はこちらです:
プロフィール:
和田晶平 スタディブレイン和歌山駅東口教室勉強コーチ
哲学と歴史が大好き 最近は中国古典にハマっている
スタディブレイン和歌山駅東口教室