ブログ
Blog
ご褒美で勉強は逆効果? 科学が教える子どもの内発的モチベーションの育て方

「テストでいい点を取ったら、新しいゲームを買ってあげる」「宿題を全部終わらせたら、お小遣いをあげる」
保護者の方々が、子どものやる気を引き出すために「ご褒美」を使うことはよくあることです。しかし、心理学と行動科学の視点から見ると、実はこの**「ご褒美(外からの報酬)」が、子どもの勉強に対する意欲をかえって削いでしまう**可能性があることが分かっています。
なぜ、善意のご褒美が逆効果になるのでしょうか?
このブログでは、子どもの「勉強への興味や楽しさ」といった**内側から湧き出る意欲(内発的モチベーション)**を、科学的に潰さず、育てるための具体的な方法を解説します。
1. 心理学が警告する「アンダーマイニング効果」とは?

もともと子どもが**「楽しい」「面白い」と感じて自発的に行っていた活動に対して、金銭や物などの「外的な報酬」を与え始めると、その活動への内的な興味が薄れてしまう現象を、心理学ではアンダーマイニング効果**(Overjustification Effect)と呼びます。
簡単に言えば、「好きだからやっていたのに、お金をもらうための仕事になってしまった」という状態です。
報酬の与え方NG例とOK例
- NG: 「勉強をしたら、ご褒美がもらえる」
- 目的が「ご褒美」にすり替わり、「勉強そのもの」への興味が失われやすくなります。
- OK: 「努力のプロセスを認め、ねぎらう」
- 報酬を与える場合は、結果に対してではなく、**「粘り強く取り組んだ」「難しい問題に挑戦した」**といったプロセスや努力そのものを承認するために与えることが重要です。
大切なのは、「報酬が目的」になることを避けることです。内発的モチベーションを育てるには、報酬ではなく、自己成長の実感に焦点を当てる必要があります。
2. 内発的な意欲を育む「自己決定理論」の3要素

子どもが「やらされている」ではなく、「自分でやっている」と感じる状態、すなわち内発的モチベーションを強く持つためには、心理学の自己決定理論によると、以下の3つの要素を満たすことが重要です。
| 満たすべき3つの要素 | 子どもに与えるべき体験 |
| ① 自律性(Autonomy) | **「自分で選んでいる」**と感じる機会 |
| ② 有能感(Competence) | **「自分はできる」**と感じる成功体験 |
| ③ 関係性(Relatedness) | **「安心して挑戦できる」**環境と信頼関係 |
自律性の尊重:**「いつ」「何を」**少しだけ選ばせる
「勉強しなさい!」という命令は、自律性を奪い、反発を生みます。子どもに内発的な意欲を持たせるには、**「自分で決めた」**という感覚を持たせることが大切です。
- 声かけNG例: 「今すぐ数学のドリルをやりなさい!」
- 声かけOK例: 「数学と英語、どちらから始める?」「勉強するのは夜ご飯の前と後、どっちにする?」
勉強の「全て」を選ばせる必要はありませんが、時間や順番、休憩のタイミングなど、ごく一部でも選択権を与えることで、**「自分の意思でやっている」**という感覚が芽生えます。
3. 有能感を高める「課題の最適化」と「具体的な承認」

「どうせやってもできない」という気持ちは、有能感が低い状態から生まれます。この感覚を変えるには、適切な成功体験を積み重ねさせることが欠かせません。
課題の最適化:**「ちょっと頑張れば届く」**難易度に設定する
課題の難易度が簡単すぎると退屈し、難しすぎるとすぐに諦めてしまいます。心理学でいう**「フロー体験」に入るためには、「自分のスキルより少しだけ難しい」**という最適な難易度を設定することが重要です。
前回の記事で紹介したスモールステップを活用し、**「今日の目標はこれだけ、でもちょっと集中しないとできないよ」**というレベルの課題を設定しましょう。達成感が、次の挑戦への意欲につながります。
具体的な承認:**「結果」ではなく「行動」**を褒める
ご褒美が内発的意欲を削ぐ原因となるなら、代わりに使うべきは**「承認」です。特に、結果ではなく努力や工夫**といった行動を具体的に褒めることで、子どもは「自分の行動は意味がある」と感じ、再びその行動を繰り返そうとします。
| NGな承認(結果への注目) | OKな承認(行動への注目) |
| 「テストで100点、すごいね!」 | 「苦手な計算を最後まで粘り強く解いた姿勢がすごい!」 |
| 「天才だね、すぐにできちゃって」 | 「昨日より10分早く勉強を始めたね、時間の使い方が上手だ!」 |
4. まとめ:内発的モチベーションを育てるための3つの原則
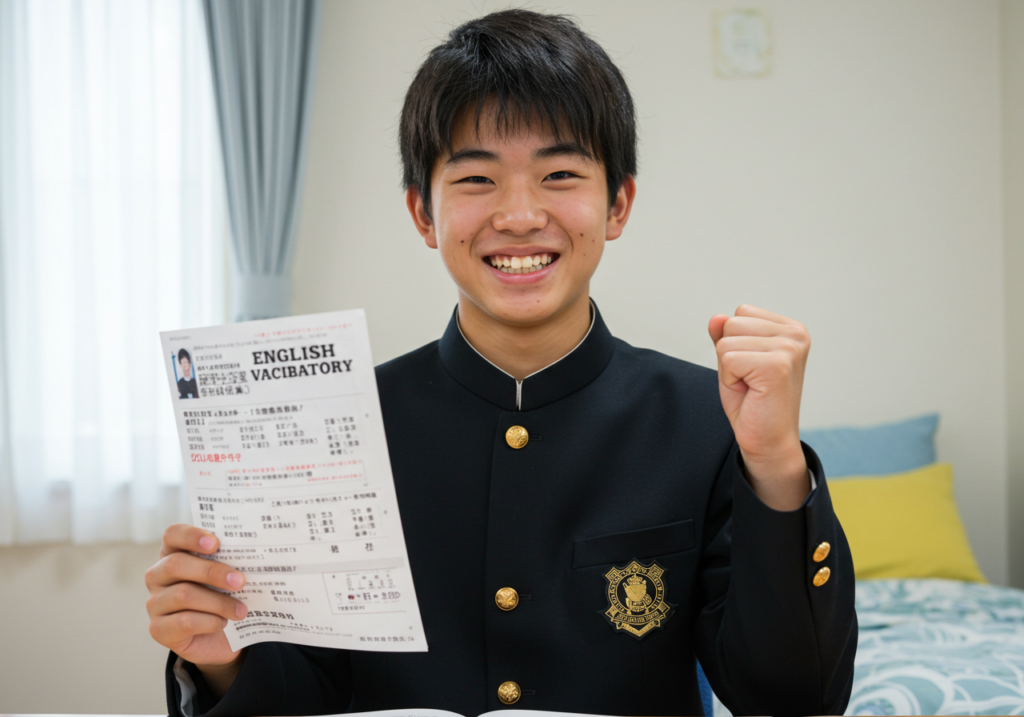
ご褒美に頼らず、子どもが自ら進んで勉強に取り組むようになるには、親や周囲の関わり方が極めて重要です。
- ご褒美は慎重に: 物的な報酬は内的な興味を削ぐ可能性がある(アンダーマイニング効果)。努力やプロセスを承認する**「言葉」**を報酬にする。
- 「自分で決める」機会を与える: 勉強の順番や時間など、小さな自律性を尊重し、自分で選んだという感覚を持たせる。
- 成功体験を積み重ねる: 「ちょっと頑張ればできる」という難易度の課題を与え、達成を通じて有能感を高める。
これらの原則に基づき、安心できる関係性を土台として、お子さんの内側から湧き出る力を引き出しましょう。
関連記事はこちらです:
プロフィール:
和田晶平 スタディブレイン和歌山駅東口教室勉強コーチ
哲学と歴史が大好き 最近は中国古典にハマっている
スタディブレイン和歌山駅東口教室
住所:〒640-8323 和歌山県和歌山市太田2丁目2−15 岡三ビル3階
ご褒美で勉強は逆効果? 科学が教える子どもの内発的モチベーションの育て方
「テストでいい点を取ったら、新しいゲームを買ってあげる」「宿題を全部終わらせたら、お小遣いをあげる」
保護者の方々が、子どものやる気を引き出すために「ご褒美」を使うことはよくあることです。しかし、心理学と行動科学の視点から見ると、実はこの**「ご褒美(外からの報酬)」が、子どもの勉強に対する意欲をかえって削いでしまう**可能性があることが分かっています。
なぜ、善意のご褒美が逆効果になるのでしょうか?
このブログでは、子どもの「勉強への興味や楽しさ」といった**内側から湧き出る意欲(内発的モチベーション)**を、科学的に潰さず、育てるための具体的な方法を解説します。
1. 心理学が警告する「アンダーマイニング効果」とは?

もともと子どもが**「楽しい」「面白い」と感じて自発的に行っていた活動に対して、金銭や物などの「外的な報酬」を与え始めると、その活動への内的な興味が薄れてしまう現象を、心理学ではアンダーマイニング効果**(Overjustification Effect)と呼びます。
簡単に言えば、「好きだからやっていたのに、お金をもらうための仕事になってしまった」という状態です。
報酬の与え方NG例とOK例
- NG: 「勉強をしたら、ご褒美がもらえる」
- 目的が「ご褒美」にすり替わり、「勉強そのもの」への興味が失われやすくなります。
- OK: 「努力のプロセスを認め、ねぎらう」
- 報酬を与える場合は、結果に対してではなく、**「粘り強く取り組んだ」「難しい問題に挑戦した」**といったプロセスや努力そのものを承認するために与えることが重要です。
大切なのは、「報酬が目的」になることを避けることです。内発的モチベーションを育てるには、報酬ではなく、自己成長の実感に焦点を当てる必要があります。
2. 内発的な意欲を育む「自己決定理論」の3要素
子どもが「やらされている」ではなく、「自分でやっている」と感じる状態、すなわち内発的モチベーションを強く持つためには、心理学の自己決定理論によると、以下の3つの要素を満たすことが重要です。
| 満たすべき3つの要素 | 子どもに与えるべき体験 |
| ① 自律性(Autonomy) | **「自分で選んでいる」**と感じる機会 |
| ② 有能感(Competence) | **「自分はできる」**と感じる成功体験 |
| ③ 関係性(Relatedness) | **「安心して挑戦できる」**環境と信頼関係 |
自律性の尊重:**「いつ」「何を」**少しだけ選ばせる
「勉強しなさい!」という命令は、自律性を奪い、反発を生みます。子どもに内発的な意欲を持たせるには、**「自分で決めた」**という感覚を持たせることが大切です。
- 声かけNG例: 「今すぐ数学のドリルをやりなさい!」
- 声かけOK例: 「数学と英語、どちらから始める?」「勉強するのは夜ご飯の前と後、どっちにする?」
勉強の「全て」を選ばせる必要はありませんが、時間や順番、休憩のタイミングなど、ごく一部でも選択権を与えることで、**「自分の意思でやっている」**という感覚が芽生えます。
3. 有能感を高める「課題の最適化」と「具体的な承認」

「どうせやってもできない」という気持ちは、有能感が低い状態から生まれます。この感覚を変えるには、適切な成功体験を積み重ねさせることが欠かせません。
課題の最適化:**「ちょっと頑張れば届く」**難易度に設定する
課題の難易度が簡単すぎると退屈し、難しすぎるとすぐに諦めてしまいます。心理学でいう**「フロー体験」に入るためには、「自分のスキルより少しだけ難しい」**という最適な難易度を設定することが重要です。
前回の記事で紹介したスモールステップを活用し、**「今日の目標はこれだけ、でもちょっと集中しないとできないよ」**というレベルの課題を設定しましょう。達成感が、次の挑戦への意欲につながります。
具体的な承認:**「結果」ではなく「行動」**を褒める
ご褒美が内発的意欲を削ぐ原因となるなら、代わりに使うべきは**「承認」です。特に、結果ではなく努力や工夫**といった行動を具体的に褒めることで、子どもは「自分の行動は意味がある」と感じ、再びその行動を繰り返そうとします。
| NGな承認(結果への注目) | OKな承認(行動への注目) |
| 「テストで100点、すごいね!」 | 「苦手な計算を最後まで粘り強く解いた姿勢がすごい!」 |
| 「天才だね、すぐにできちゃって」 | 「昨日より10分早く勉強を始めたね、時間の使い方が上手だ!」 |
4. まとめ:内発的モチベーションを育てるための3つの原則
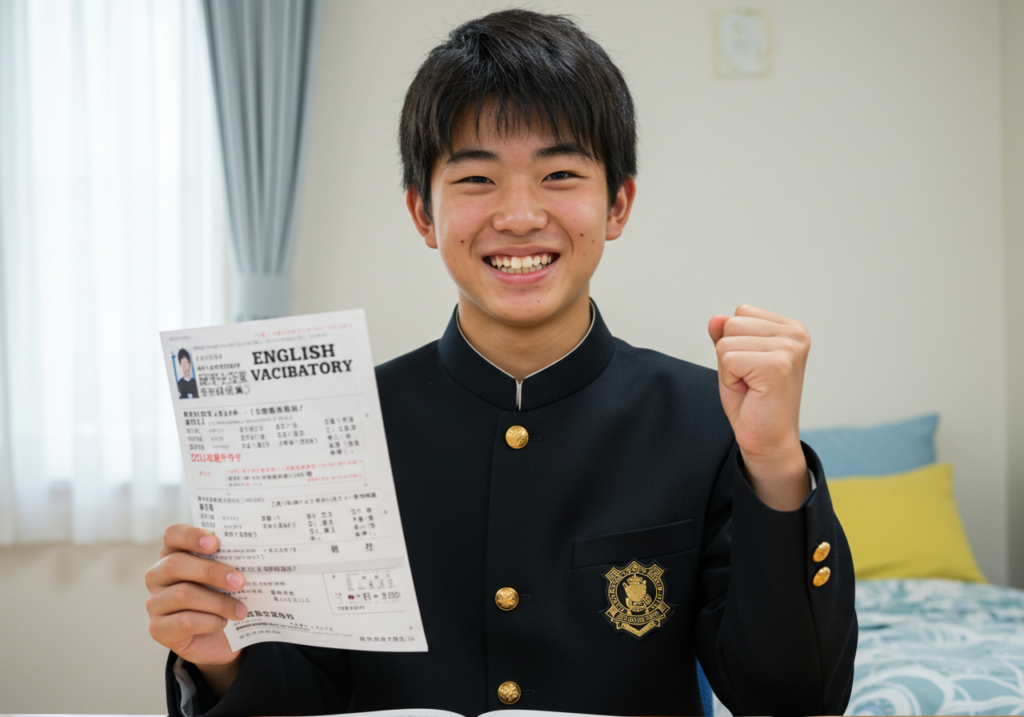
ご褒美に頼らず、子どもが自ら進んで勉強に取り組むようになるには、親や周囲の関わり方が極めて重要です。
- ご褒美は慎重に: 物的な報酬は内的な興味を削ぐ可能性がある(アンダーマイニング効果)。努力やプロセスを承認する**「言葉」**を報酬にする。
- 「自分で決める」機会を与える: 勉強の順番や時間など、小さな自律性を尊重し、自分で選んだという感覚を持たせる。
- 成功体験を積み重ねる: 「ちょっと頑張ればできる」という難易度の課題を与え、達成を通じて有能感を高める。
これらの原則に基づき、安心できる関係性を土台として、お子さんの内側から湧き出る力を引き出しましょう。
関連記事はこちらです:
プロフィール:
和田晶平 スタディブレイン和歌山駅東口教室勉強コーチ
哲学と歴史が大好き 最近は中国古典にハマっている
スタディブレイン和歌山駅東口教室