ブログ
Blog
「やっても無駄」から卒業! 脳科学が教える記憶に残りやすい勉強法
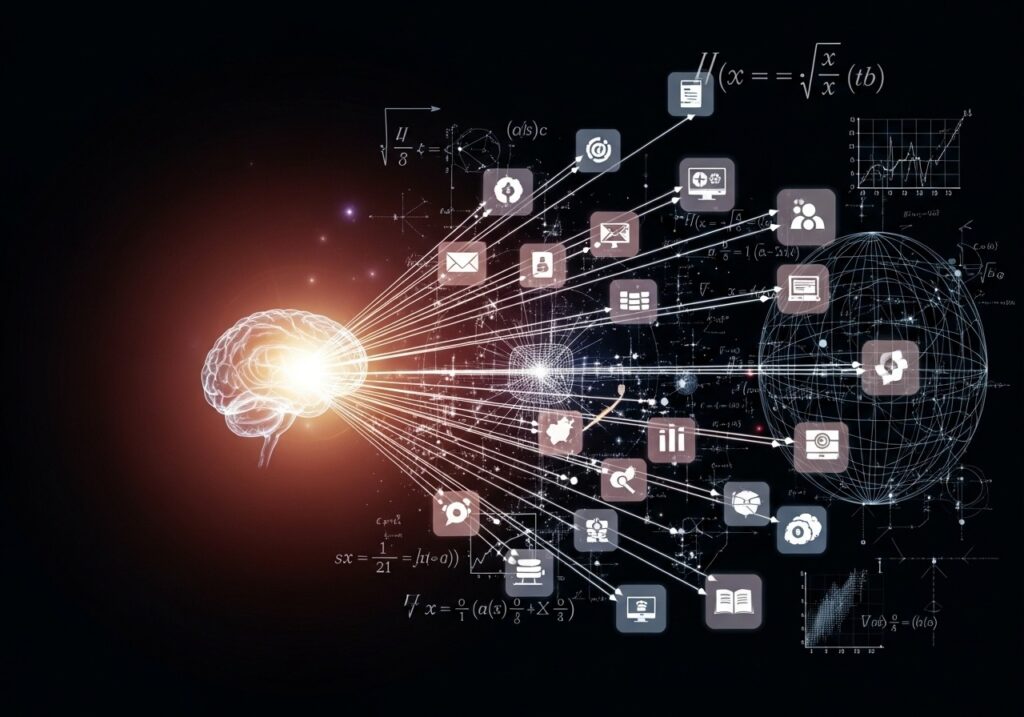
「毎日頑張って勉強しているのに、テストになるといつも忘れている…」「うちの子は長い時間机に向かっているのに、結果が伴わない」
もしあなたが、インプットに費やした努力が、成績や結果としてアウトプットされないことに悩んでいるなら、それは**「やる気」や「能力」の問題ではありません**。脳科学と認知科学の視点から見ると、それは**「記憶の仕方」**が非効率的だからかもしれません。
脳は、ただ漫然とテキストを眺めているだけでは、大事な情報と認識してくれません。このブログでは、無駄な努力を劇的に減らし、頑張りが確実に結果に結びつくようになるための、科学的に証明された**「記憶の定着率を上げる3つの学習テクニック」**を、平易な言葉で解説します。
1. 記憶の土台を固める「分散学習(スペーシング効果)」

多くの生徒は、テスト直前になって大量の情報を詰め込もうとします(これを集中学習と呼びます)。しかし、脳科学的には、これは最も効率の悪い方法です。一夜漬けで覚えた情報は、一時的に記憶されますが、すぐに忘れてしまうことがわかっています。
脳が情報を長期記憶として定着させるには、時間の経過が必要です。
スペーシング効果:少しずつ、間隔を空けて繰り返す
分散学習(スペーシング効果)とは、同じ学習内容を短い期間で一気に繰り返すのではなく、適切な間隔を空けて、何度も思い出す機会を作る学習法です。
| NGな学習法(集中学習) | OKな学習法(分散学習) |
| テスト前日に歴史の用語を3時間かけ て一気に覚える | 毎日10分だけ歴史の用語を見直し、1日、3日、1週間後と間隔を空けて復習する |
| 週末に数学の問題集をまとめて解き終 える | 平日に毎日2題ずつ問題を解き、次の週にもう一度解き直す |
ポイント: **「忘れる前に、もう一度思い出す」**ことが脳を刺激します。間隔を空けることで、脳は「この情報は時間が経っても必要な情報だ」と判断し、記憶を強固に定着させます。
2. 記憶を引っ張り出す訓練「検索練習(テスト効果)」
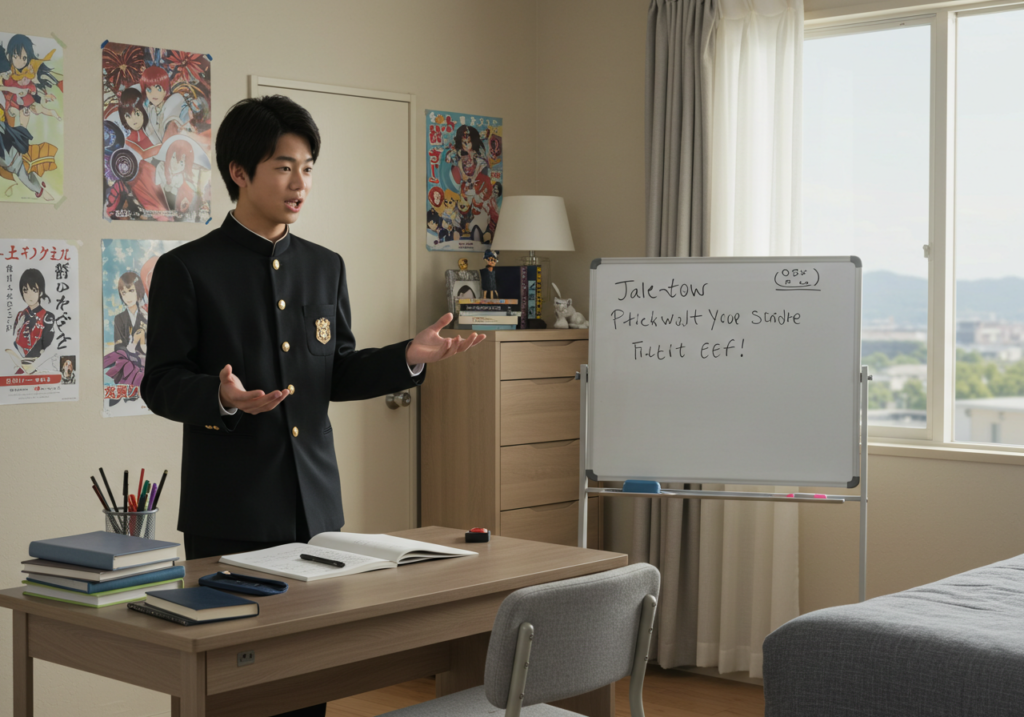
教科書を読んだり、ノートを色ペンでまとめたりする行為(インプット)は、勉強している気分にはなれますが、実は記憶の定着にはあまり役立たないことが分かっています。
本当に記憶に残りやすいのは、「思い出す」というアウトプットの作業です。
テスト効果:クイズやセルフチェックで脳に負荷をかける
検索練習(テスト効果)とは、テキストを閉じて、覚えたことを自力で思い出そうと試みる学習法です。これは、単なるテスト対策ではなく、記憶自体を強くするための強力な訓練です。
- セルフチェック: テキストやノートを閉じ、キーワードだけを見て、内容を口頭で説明してみる。
- フラッシュカード: 問題面を見て、答えを頭の中で完全に思い出すまでカードを裏返さない。
- 過去問活用: まだ習っていない範囲でも、過去問を見て**「何が問われているか」**を考える。
ポイント: テスト効果は、思い出す過程で「間違いやすい箇所」を特定できるため、効率的な復習につながります。苦労して思い出した情報ほど、脳はそれを「重要だ!」と認識し、長期記憶に刻み込みます。
3. 脳を飽きさせない学習法「インターリービング」

一つの科目を長時間続けていると、集中力が落ちて「作業効率」が低下します。これは、脳が同じ種類の情報処理に飽きてしまうためです。
認知科学では、複数の異なるスキルや分野を短い時間で切り替えながら学習する「インターリービング(interleaving=混ぜ合わせる)」が効果的だとされています。
インターリービング:複数科目を「混ぜて」取り組む
インターリービングは、問題を解く際に特に有効です。同じ種類の問題が続くドリルではなく、異なる種類の問題や科目を交互に取り組むことで、脳の活性化を促します。
| NGな学習法(ブロッキング) | OKな学習法(インターリービング) |
| 3時間:数学の関数問題だけを 解き続ける | 1時間目:数学(関数) → 2時間目:英語(文法) → 3時間目:数学(確率)と 科目を切り替える |
| 1週間:単語の暗記だけに集中 する | 1週間:午前中に単語暗記、午後に長文読解、夜に文法と種類を混ぜる |
ポイント: 複数の情報を混ぜると、一見非効率に見えますが、脳は科目ごとの違いを見分けようとするため、深く考えるようになります。その結果、知識の応用力や問題解決能力も同時に鍛えられます。
4. まとめ:頑張りを成果に変える脳科学的勉強法
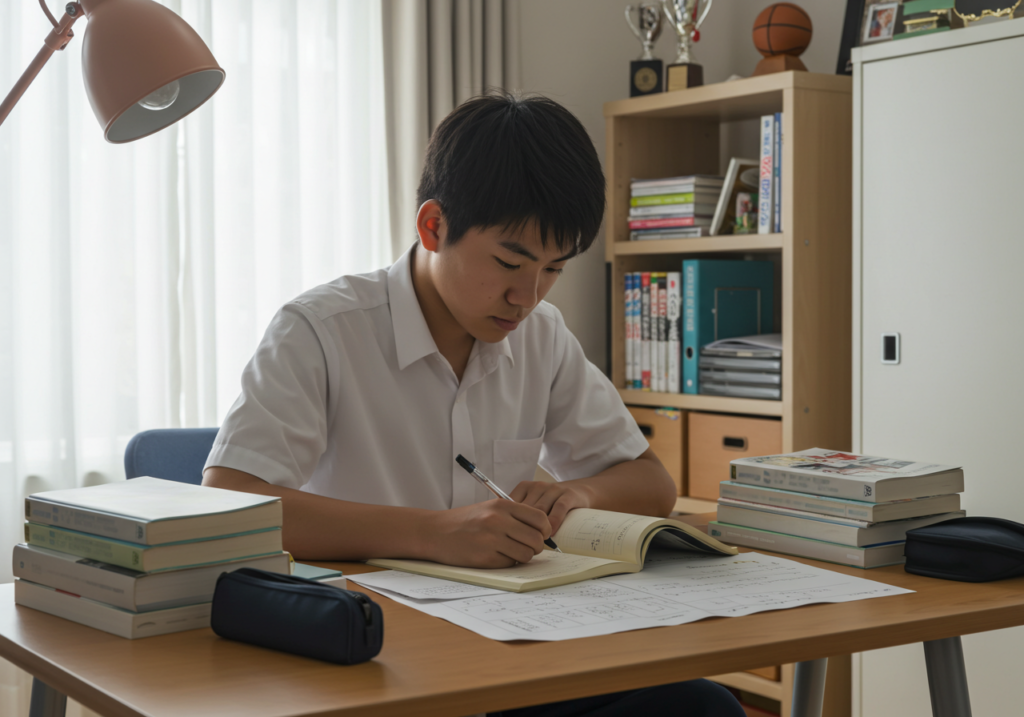
無駄な努力を卒業し、頑張りを結果に変えるためには、**「いつ」「どうやって」**勉強するかを科学的に最適化することが重要です。
- **「分散学習」**で時間をかけて繰り返し、記憶の土台を固める。
- **「検索練習」**で積極的に思い出す訓練をし、記憶を強固にする。
- **「インターリービング」**で科目を混ぜ、脳を活性化させ、応用力を高める。
これら3つの方法を取り入れることで、あなたの、またはお子さんの勉強は、きっと今よりも少ない時間で、より大きな成果を生み出すようになるでしょう。
関連記事はこちらです:
プロフィール:
和田晶平 スタディブレイン和歌山駅東口教室勉強コーチ
哲学と歴史が大好き 最近は中国古典にハマっている
スタディブレイン和歌山駅東口教室